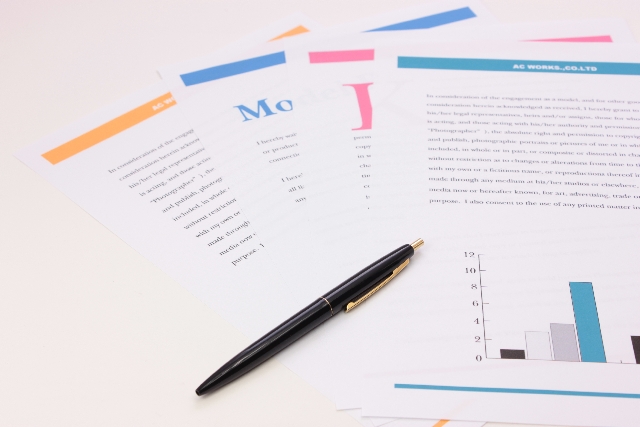


会社役員のメリット デメリットとはなんでしょうか?
私は小さな会社の一応会社役員ですが、役員報酬があるわけでも有りませんし、ただ毎月の給料のために働いているのが、現状です。株を沢山保有しているわけではありません、ただ株式会社を成立させる為の役員ってことです。言ってみれば代表の独り占めですね、経費を使えるって事もありませんし、このままつずけていて良いことが有るのでしょうか?役員ですと、失業保険も加入出来ないと聞いていますし・・・給料明細は恥ずかしい話ですが、基本給から取得税が引かれているだけです、これってアルバイトと同じなのかな?なんて最近考えています、いい様に雇われているだけなのですかね?何か会社にダメージの大きい発言はあるものでしょうか?又会社は何を言われると困るものでしょうか?どなたか私にいい知恵を教えてください。
私は小さな会社の一応会社役員ですが、役員報酬があるわけでも有りませんし、ただ毎月の給料のために働いているのが、現状です。株を沢山保有しているわけではありません、ただ株式会社を成立させる為の役員ってことです。言ってみれば代表の独り占めですね、経費を使えるって事もありませんし、このままつずけていて良いことが有るのでしょうか?役員ですと、失業保険も加入出来ないと聞いていますし・・・給料明細は恥ずかしい話ですが、基本給から取得税が引かれているだけです、これってアルバイトと同じなのかな?なんて最近考えています、いい様に雇われているだけなのですかね?何か会社にダメージの大きい発言はあるものでしょうか?又会社は何を言われると困るものでしょうか?どなたか私にいい知恵を教えてください。
役員の立場というか役員はどういう役割なのかが会社の約款に載っているはずです。
うちの場合は執行部(事実上役員会は承認の場になってしまっていますが…)ですので会社の運営に関することを職員と一体となり協議することができます。
しかし会社に多大な損失が生じた場合には責任を負うことになりかねないリスクもありますので、本来ならば形だけの役員ではなく事実上の執行部となってほしいものです。
うちの場合は執行部(事実上役員会は承認の場になってしまっていますが…)ですので会社の運営に関することを職員と一体となり協議することができます。
しかし会社に多大な損失が生じた場合には責任を負うことになりかねないリスクもありますので、本来ならば形だけの役員ではなく事実上の執行部となってほしいものです。
扶養家族手続きについて教えてください。
結婚により2014年9月末日で退職しました。
今年度の年収が130万超えており2014年度は扶養家族となることが出来ず、健康保険料を今まで勤務していた健康保険組合に10月から毎月36000円程支払っております(国保にすると毎月50000円位の支払が必要と言われました)。
今のところ次の就職先も決まっておらず、2015年1月から主人の扶養家族になることを希望してます(失業保険は2015年2月から3か月130万未満受給予定です)。
健康保険組合に退職後の延長手続きをした際、次の勤務先が決まるまで退会できないと言われてましたが、主人の扶養家族となり健康保険組合に退会申し出することはできるのでしょうか?
可能であればどのような手続きが必要でしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
結婚により2014年9月末日で退職しました。
今年度の年収が130万超えており2014年度は扶養家族となることが出来ず、健康保険料を今まで勤務していた健康保険組合に10月から毎月36000円程支払っております(国保にすると毎月50000円位の支払が必要と言われました)。
今のところ次の就職先も決まっておらず、2015年1月から主人の扶養家族になることを希望してます(失業保険は2015年2月から3か月130万未満受給予定です)。
健康保険組合に退職後の延長手続きをした際、次の勤務先が決まるまで退会できないと言われてましたが、主人の扶養家族となり健康保険組合に退会申し出することはできるのでしょうか?
可能であればどのような手続きが必要でしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
1.掲載済みのご回答の通りですが、少し補足をさせていただきます。
2.健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者扱いについて、間違ったご理解をされております。
3.所得税額の計算のように暦年単位ではありません。
4.具体例で回答いたします。
5.例えば、平成26年1月~9月迄に、500万円の給与支払額<賞与を含む>があったと仮定します。この給与支払額では、ご主人は、所得税額において配偶者控除も配偶者特別控除も申告することは出来ません。
6.しかし、平成26年10月以降、無職になる場合は、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者扱いの申請が可能であり、受理されると思います。
7.退職後に雇用保険の基本手当を受け取る場合は、日額相当=3,612円未満、月額相当=108,333円未満であれば、申請は可能です。日額=130万円÷12か月÷30日、月額=130万円÷12か月で計算します。
以上
2.健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者扱いについて、間違ったご理解をされております。
3.所得税額の計算のように暦年単位ではありません。
4.具体例で回答いたします。
5.例えば、平成26年1月~9月迄に、500万円の給与支払額<賞与を含む>があったと仮定します。この給与支払額では、ご主人は、所得税額において配偶者控除も配偶者特別控除も申告することは出来ません。
6.しかし、平成26年10月以降、無職になる場合は、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者扱いの申請が可能であり、受理されると思います。
7.退職後に雇用保険の基本手当を受け取る場合は、日額相当=3,612円未満、月額相当=108,333円未満であれば、申請は可能です。日額=130万円÷12か月÷30日、月額=130万円÷12か月で計算します。
以上
退職後の仕事と失業保険についての質問です。
私は来年の10月に沖縄に嫁ぐ予定の為、来年の3月に退職したいと考えています。(勤務年数は2年)
上司に相談したところ、結婚ということで『会社都合』にしていただけるとのことでした。
9月ギリギリまで今の仕事すればよいのですが、結婚や引越しの準備などの為、きりのいい3月に退職し、その後は派遣かアルバイトで働こうと考えています。
沖縄へ引越しが済んだ後に正式に就職活動をするつもりですので、10月(もしくは9月)から失業保険をもらいたいのです。
そこで質問ですが、
①前職を辞めて、申請のためハローワークに行くまでに仕事をしても通常通りの失業保険はもらえるのでしょうか?
②①でいう仕事とは「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」かつ「1日4時間以内」でないといけないのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
私は来年の10月に沖縄に嫁ぐ予定の為、来年の3月に退職したいと考えています。(勤務年数は2年)
上司に相談したところ、結婚ということで『会社都合』にしていただけるとのことでした。
9月ギリギリまで今の仕事すればよいのですが、結婚や引越しの準備などの為、きりのいい3月に退職し、その後は派遣かアルバイトで働こうと考えています。
沖縄へ引越しが済んだ後に正式に就職活動をするつもりですので、10月(もしくは9月)から失業保険をもらいたいのです。
そこで質問ですが、
①前職を辞めて、申請のためハローワークに行くまでに仕事をしても通常通りの失業保険はもらえるのでしょうか?
②①でいう仕事とは「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」かつ「1日4時間以内」でないといけないのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
4月以降の仕事(パートでも)で雇用保険に加入するような本格的な勤務の場合は
9月に沖縄のハローワークで申請した際に失格とされてしまいます。
ですので9月(6月とか)まで継続して今のまま働くかあるいは4月からハローワークに行くかどちらかです。
9月に沖縄のハローワークで申請した際に失格とされてしまいます。
ですので9月(6月とか)まで継続して今のまま働くかあるいは4月からハローワークに行くかどちらかです。
失業保険について
今失業保険の延長をしているものです。
90日間失業保険をもらえるのですが、90日分いっきに振り込まれるのでしょうか?
それとも週ごとなのか、月ごとなのか・・・
決められた給付日とかがあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
今失業保険の延長をしているものです。
90日間失業保険をもらえるのですが、90日分いっきに振り込まれるのでしょうか?
それとも週ごとなのか、月ごとなのか・・・
決められた給付日とかがあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
延長を解除してください。
そうして認定日が決まります。
その認定日の認定日数が認定日から5営業日以内に振り込まれます。
最初は半端な日数になりますが通常は28日ごとに認定日があってその分が振り込まれます。
例を上げますと、最初14日(仮に)+28日+28日+20日=90日のように4回の支給になります。
そうして認定日が決まります。
その認定日の認定日数が認定日から5営業日以内に振り込まれます。
最初は半端な日数になりますが通常は28日ごとに認定日があってその分が振り込まれます。
例を上げますと、最初14日(仮に)+28日+28日+20日=90日のように4回の支給になります。
夫が失業して毎日家にいます。
毎日朝方までインターネットやゲームをして昼二時、三時まで寝てるようです。
私はバイトで働いてるのですが、その姿にがっかりなのか、なんとも言えない不安と冷めた気持ちになります。
今まではバイトが終わって、夕飯の支度して、夫が帰ってくるという生活をしていたのですが、
今帰ってくると必ず夫がいて、1日なにしてるのかわからない上にやる気も感じられないのを見ると、夕飯を作る気になりません。
夫は黙って仕事を辞め、最初は行ってるふりをしました。
だんだんほころびが出てきて私から問いつめました。
ある程度就活しながら辞めるならまだしも、がっちり失業保険を全部もらってから決めよう、みたいな所が見えます。
私は将来やお金の不安というか、夫との不安で毎日疲れがとれず、仕事の量と時間も増やしたことにより、体力も精神もきついです。
次喧嘩でもしたら本当になにかが切れてしまいそうです。
とにかく一緒にいたくないので、疲れて家でゆっくりしたくても夫がいるので、できるだけ出かけるようにしてたら本当に休まりません…
こういう時期はどうやって乗り越えるべきか、
冷めた気持ちはどうやって取り戻したらよいか
アドバイス下さい!
離婚は本当に最終手段にしたいです。
毎日朝方までインターネットやゲームをして昼二時、三時まで寝てるようです。
私はバイトで働いてるのですが、その姿にがっかりなのか、なんとも言えない不安と冷めた気持ちになります。
今まではバイトが終わって、夕飯の支度して、夫が帰ってくるという生活をしていたのですが、
今帰ってくると必ず夫がいて、1日なにしてるのかわからない上にやる気も感じられないのを見ると、夕飯を作る気になりません。
夫は黙って仕事を辞め、最初は行ってるふりをしました。
だんだんほころびが出てきて私から問いつめました。
ある程度就活しながら辞めるならまだしも、がっちり失業保険を全部もらってから決めよう、みたいな所が見えます。
私は将来やお金の不安というか、夫との不安で毎日疲れがとれず、仕事の量と時間も増やしたことにより、体力も精神もきついです。
次喧嘩でもしたら本当になにかが切れてしまいそうです。
とにかく一緒にいたくないので、疲れて家でゆっくりしたくても夫がいるので、できるだけ出かけるようにしてたら本当に休まりません…
こういう時期はどうやって乗り越えるべきか、
冷めた気持ちはどうやって取り戻したらよいか
アドバイス下さい!
離婚は本当に最終手段にしたいです。
失業保険をもらおうとしているのは金銭感覚があることです
本当は就活あせっても、あせりすぎることはない状態なのですがね
まあ、お歳暮仕分けなどの仕事もコチョコチョ入る時期なので短期バイトでもしてもらったらいかがでしょう・・・
実際に働くのはもう少し後ですが少しずつアルバイトの募集が始まるはずです
雇用保険法をお勉強して(本屋に行けば社会保険労務士の試験用の本が平積みです)
納得して働いてもらいましょう
失業保険をもらいきれば働くのですね
失業保険をもらえるまで一生懸命に働いた
すばらしいじゃないですか
長期休暇だと思って大目に見てはいかがでしょうか
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
あと、家事ぐらいしてもらいましょう。。。。。。。。
本当は就活あせっても、あせりすぎることはない状態なのですがね
まあ、お歳暮仕分けなどの仕事もコチョコチョ入る時期なので短期バイトでもしてもらったらいかがでしょう・・・
実際に働くのはもう少し後ですが少しずつアルバイトの募集が始まるはずです
雇用保険法をお勉強して(本屋に行けば社会保険労務士の試験用の本が平積みです)
納得して働いてもらいましょう
失業保険をもらいきれば働くのですね
失業保険をもらえるまで一生懸命に働いた
すばらしいじゃないですか
長期休暇だと思って大目に見てはいかがでしょうか
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
あと、家事ぐらいしてもらいましょう。。。。。。。。
失業保険 受給資格についてお訪ねします。
自己都合で退職した場合
半年の勤務年数では
支給されませんか?
自己都合だと 最低 1年間 会社が掛けてないと
支給されないんですね?
自己都合で退職した場合
半年の勤務年数では
支給されませんか?
自己都合だと 最低 1年間 会社が掛けてないと
支給されないんですね?
正確に言いますと、勤務年数ではなく雇用保険被保険者期間です。
例えば試用期間が勤務年数に入る場合でもその間に雇用保険に加入していなければその期間は外れます。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。(6ヶ月ではだめです)
ただし、自己都合であっても「特定理由離職者」に該当すれば、過去1年間に6ヶ月以上の期間があれば受給資格はあります。
その場合は給付制限3ヶ月はつかず、支給日数もH24年3月31日までは特例期間ですから会社都合と同様になり優遇されます。
例えば試用期間が勤務年数に入る場合でもその間に雇用保険に加入していなければその期間は外れます。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。(6ヶ月ではだめです)
ただし、自己都合であっても「特定理由離職者」に該当すれば、過去1年間に6ヶ月以上の期間があれば受給資格はあります。
その場合は給付制限3ヶ月はつかず、支給日数もH24年3月31日までは特例期間ですから会社都合と同様になり優遇されます。
関連する情報